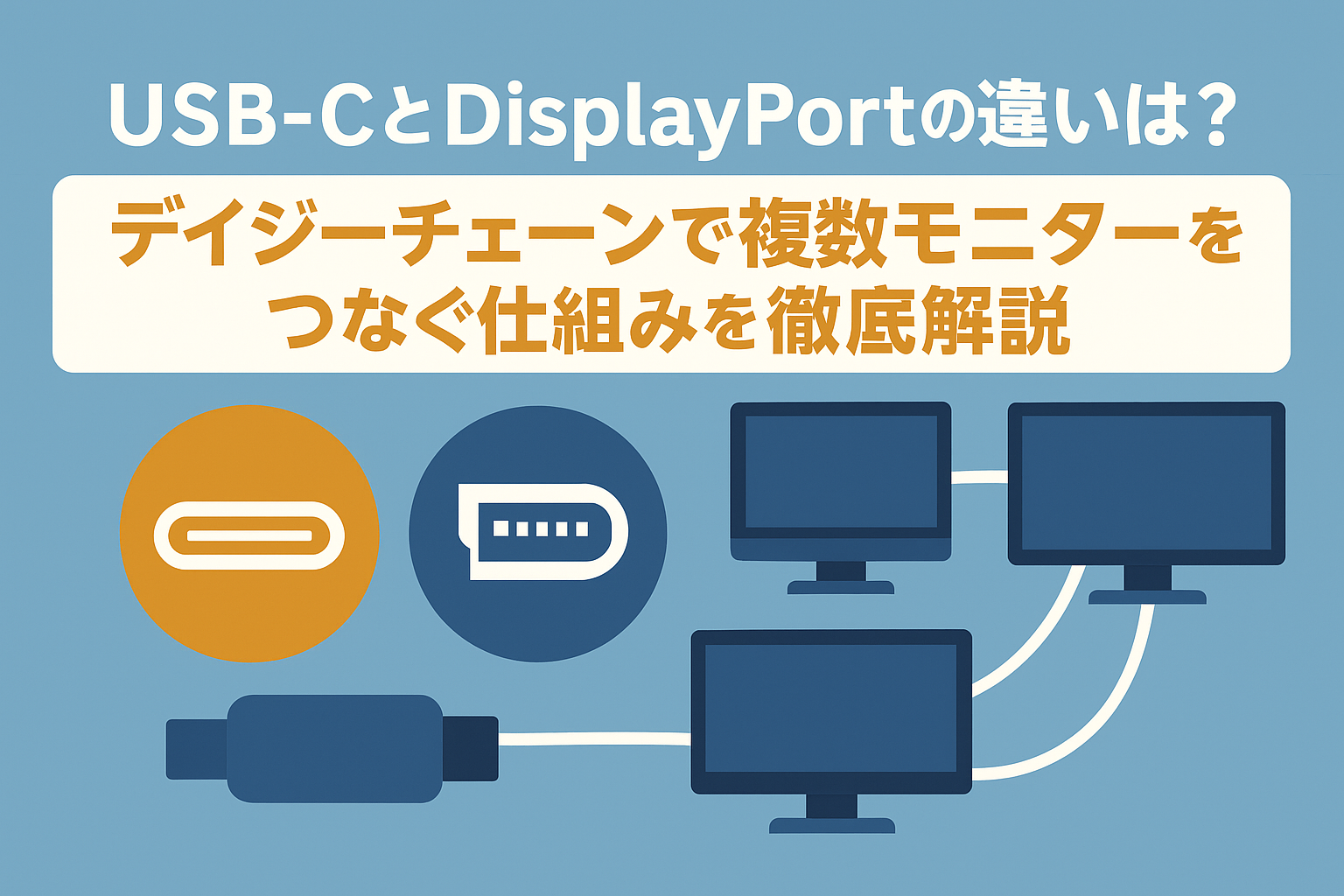こんにちは、七宮さん@Shichinomiya_sです。
先日、DELLのハイエンドモニターを購入し、デイジーチェーン接続を試してみたところ、想像以上に奥が深く、沼にハマりました。
今回、調べた内容を備忘録としてまとめました。DisplayPort周辺の仕様に悩んでいる方の参考になれば幸いです。
DisplayPortの基本知識
端子形状
DisplayPortには主に以下の3種類の端子形状が存在します。
・PC用グラフィックボード:DisplayPort
・Macなど:mini DisplayPort
・最近のノートPC:USB Type-C(DP Alt Mode対応)

特に重要なのが USB Type-C/Thunderbolt 端子 です。
USB-Cには「DisplayPort Alt Mode」という映像出力規格があり、これに対応したUSB-CのみがDisplayPortとして動作します。
そのため、USB-Cだからといって必ず映像出力に使えるわけではなく、「Alt Mode対応かどうか」「ポートとして映像出力に割り当てられているか」を確認する必要があります。
USB-C Alt Mode対応の確認方法
お使いのデバイスがDisplayPort Alt Modeに対応しているかを確認する方法:
・ポート横のアイコン確認:DisplayPortまたはThunderboltのアイコンがあればAlt Mode対応
・製品仕様書を確認:メーカーの公式仕様に「DisplayPort Alt Mode」「DP Alt Mode」の記載があるか
・デバイスマネージャーで確認(Windows):USB-Cポートのプロパティで「Alternate Mode」の記載を確認
・システム情報で確認(Mac):「このMacについて」→「システムレポート」→「USB」で確認
注意:充電専用のUSB-Cポートは映像出力に対応していないことが多いです。
DisplayPortのバージョン情報
DisplayPortには複数のバージョンが存在し、バージョンによって最大帯域幅や出力可能解像度が変わります。
| DPバージョン | データ転送速度規格 | レーン数 | 最大仕様帯域幅 | 最大有効帯域幅 |
| 1.2 | HBR2 | 4 | 21.6 Gbps (5.4 Gbps × 4) | 17.28 Gbps (4.32 Gbps × 4) |
| 1.3/1.4 | HBR3 | 4 | 32.4 Gbps (8.1 Gbps × 4) | 25.92 Gbps (6.48 Gbps × 4) |
| 2.1 | UHBR10/UHBR13.5/UHBR20 | 4 | 40 Gbps/54 Gbps/80 Gbps(2.1仕様) | 約38.7/52.2/77.4 Gbps(128b/132b符号化後) |
※DP 2.1では、従来の8b/10b符号化から「128b/132b符号化」に移行されており、帯域効率が向上しています。
※ケーブルおよびデバイスの実装次第で、UHBR13.5/UHBR20をサポートしているかは機器により異なります。
DisplayPortケーブルの選び方
DisplayPortケーブルを選ぶ際には、以下のポイントに注意が必要です。
ケーブルの認証マーク
VESA(Video Electronics Standards Association)が認証したケーブルには以下のマークがあります:
・Certified DisplayPort Cable:DP 1.2/1.4対応の認証済みケーブル
・DP40 / DP54 / DP80:DP 2.1対応ケーブルの新しい認証(40/54/80 Gbpsに対応)
認証マークがないケーブルは、表記されている仕様を満たさない場合があります。
ケーブル長による制限
DisplayPortケーブルの長さによって、対応できる解像度や帯域幅が変わります。
・1m以内:ほぼ全てのケーブルで最大仕様を発揮可能
・2m以内:DP 1.4で4K 60Hz、DP 2.1でUHBR20までサポート(品質の良いケーブル)
・3m以上:ケーブル品質により帯域が制限される場合あり。長距離の場合はアクティブケーブルを推奨
重要:デイジーチェーンでは複数のケーブルを使用するため、各ケーブルの品質が全体のパフォーマンスに影響します。
パッシブケーブル vs アクティブケーブル
・パッシブケーブル:通常のケーブル。2m以下の使用に適している
・アクティブケーブル:信号増幅機能を内蔵。3m以上や4K 120Hz以上の高帯域幅が必要な場合に推奨
USB-C to DisplayPortケーブルの注意点
USB-C to DisplayPortケーブルを使用する場合:
・USB-Cポート側がDisplayPort Alt Mode対応である必要がある
・ケーブルのDP対応バージョン(1.2/1.4/2.1)を確認する
・双方向対応か一方向のみかを確認(一方向の場合、USB-C→DPの向きが決まっている)
・Thunderbolt 3/4対応ケーブルはDisplayPort信号も伝送可能
MSTとSSTの違い
MST(Multi Stream Transport)
DisplayPort 1.2から搭載された機能で、「1つの出力端子から複数の映像信号を出力できる」仕組みです。
例:デイジーチェーン、MST対応ハブなど。
複数モニターを1ポートから繋げたい場合はこの方式が使われます。
MSTのメリット
・PCの映像出力ポートが少なくても複数モニターを接続可能
・ケーブル配線がすっきりする
・1つのポートから最大4台までのモニターに分配可能(理論上)
MSTのデメリット・注意点
・モニター側がMST対応である必要がある
・帯域幅を複数のモニターで分け合うため、高解像度・高リフレッシュレートでは制限を受ける
・G-SyncやFreeSyncなどの可変リフレッシュレート技術が使えない場合がある
・一部のアプリケーション(特に一部のゲーム)でMSTとの互換性問題が発生することがある
SST(Single Stream Transport)
従来方式で、1つの出力端子から1つの映像信号を出力するというもの。MSTが登場してから、区別のために「SST」という言葉が使われるようになりました。
SSTのメリット
・全ての帯域幅を1つのモニターで使用可能
・G-Sync、FreeSync等の可変リフレッシュレート技術に対応
・互換性の問題が少ない
・ゲーミング用途に最適
SSTのデメリット
・複数モニターを接続する場合、各モニターごとに個別のポートとケーブルが必要
・PCの映像出力ポート数に制限される
MST vs SST:どちらを選ぶべきか
| 用途 | MST推奨 | SST推奨 |
| ゲーミング | – | ○(G-Sync/FreeSync対応) |
| オフィスワーク・マルチタスク | ○(複数モニター接続が容易) | △(ポート数が足りれば) |
| クリエイティブ作業 | △(色精度重視ならSST) | ○ |
| ポータブルPC + 複数モニター | ○(ポート数が限られる) | △ |
DisplayPortにおけるデイジーチェーンとは
PCから各モニターへ1本ずつケーブルを繋ぐ代わりに、以下のように「数珠つなぎ」で接続する方法です。
PC → モニター1 → モニター2 → モニター3 → …
この場合、モニター1からモニター2への出力が可能な「出力端子付きモニター」やMST対応機器が必要です。
この方式により、PCの映像出力ポートが1つしかなくても複数モニターを繋げられ、配線もすっきりします。
(出典:EIZO – デイジーチェーン対応モニターの導入ガイド)
デイジーチェーンの必要条件
デイジーチェーン接続を行うには、以下の条件を満たす必要があります:
1. GPU/SoCがMSTに対応していること(DP 1.2以降)
2. モニターがMST対応であること(DisplayPort Outポートを搭載)
3. 使用するケーブルがDP 1.2以降に対応していること
4. OSがマルチモニターをサポートしていること(Windows 7以降、macOS 10.11以降など)
注意:macOSの一部バージョンではMSTのサポートが制限されており、Boot CampでWindowsを使用する場合のみMSTが利用できることがあります。最新のmacOS対応状況は公式サイトで確認してください。
デイジーチェーンの設定手順
【Windows環境での設定】
ステップ1:物理的な接続
1. PCのDisplayPortまたはUSB-C(Alt Mode対応)から、最初のモニターのDisplayPort Inに接続
2. 最初のモニターのDisplayPort Outから、2台目のモニターのDisplayPort Inに接続
3. さらにモニターを追加する場合は、2台目のDisplayPort Outから3台目に接続
ステップ2:モニター側の設定
1. 各モニターのOSD(On-Screen Display)メニューを開く
2. 「DisplayPort」設定を探す
3. 最後のモニター以外は「DisplayPort 1.2 MST」または「DP MST」を有効にする
4. 最後のモニター(チェーンの終端)は「DP MST」を無効にする
ステップ3:Windows側の設定
1. デスクトップを右クリック →「ディスプレイ設定」を開く
2. 「マルチディスプレイ」の項目で「表示画面を拡張する」を選択
3. 各モニターの配置や解像度を調整
4. 「検出」ボタンを押して、すべてのモニターが認識されているか確認
【macOS環境での設定(対応機種のみ)】
1. 物理的な接続はWindowsと同様
2. システム環境設定 →「ディスプレイ」を開く
3. 「配置」タブでモニターの配置を調整
4. 各モニターの解像度を確認・調整
注意:多くのMacではMST方式のデイジーチェーンがサポートされていません。Thunderbolt Displayのデイジーチェーン(別方式)は可能です。
デイジーチェーン接続時の注意点
・最終モニターはMSTを無効にする:最後のモニターでMSTを有効にしたままだと、信号が正しく終端されず、表示が不安定になることがあります
・モニターの電源投入順序:PCを起動する前に、すべてのモニターの電源を入れておくと認識されやすくなります
・ケーブルの品質:複数のモニターで帯域を共有するため、各ケーブルが規格に適合している必要があります
・解像度の制限:チェーン全体で使用できる帯域幅に制限があるため、高解像度モニターを複数接続すると、リフレッシュレートや色深度が制限される場合があります
デイジーチェーンで接続できる枚数
まず、各解像度・リフレッシュレートに必要な帯域を以下にまとめます。
| 解像度 | 帯域幅(参考値) |
| 1920 x 1080 (FHD, 60Hz) | 3.20 Gbps |
| 2560 x 1440 (WQHD 2K, 60Hz) | 5.63 Gbps |
| 3840 x 2160 (UHD 4K, 60Hz) | 12.54 Gbps |
これを基に、DisplayPortの有効帯域から「最大何枚接続できるか」をざっくり見ると以下のようになります。
| DPバージョン | 1920 x 1080 (FHD) |
2560 x 1440 (WQHD) |
3840 x 2160 (4K) |
| DP 1.2 | 4枚 | 2枚 | 1枚 |
| DP 1.3 / 1.4 | 8枚 | 2枚 | 2枚 |
| DP 2.1(UHBR10相当) | 12枚以上(理論) | 4枚以上(理論) | 3〜4枚以上(理論、但し実装次第) |
※DP 2.1の「3〜4枚以上(理論)」というのは、帯域上は余裕があるものの実装(モニター側のデイジーチェーン端子有無、MST対応、ケーブル・GPU/SoC側の制限)に大きく左右されます。
※また、4Kを240Hzなど高リフレッシュで出す場合はDSC(Display Stream Compression)等を併用するケースも増えています。
なお、実際には CPU/GPUの出力回路の制限 が優先されるため、仕様だけで「何枚でも繋げる」という訳ではありません。
帯域幅の詳細計算方法
DisplayPortで必要な帯域幅は、以下の式で概算できます:
帯域幅 = 解像度(横×縦) × リフレッシュレート × 色深度 × オーバーヘッド係数
具体例:4K 60Hz 8bit(標準)の場合
・解像度:3840 × 2160 = 8,294,400 ピクセル
・リフレッシュレート:60Hz
・色深度:24bit(8bit × RGB)
・オーバーヘッド:約1.25倍(ブランキング期間等)
計算:8,294,400 × 60 × 24 × 1.25 ÷ 1,000,000,000 ≒ 12.54 Gbps
色深度による違い
| 色深度 | 1ピクセルあたりのビット数 | 4K 60Hzでの帯域 |
| 8bit(SDR標準) | 24bit | 約12.54 Gbps |
| 10bit(HDR) | 30bit | 約15.68 Gbps |
| 12bit(プロフェッショナル) | 36bit | 約18.81 Gbps |
このため、HDRコンテンツを扱う場合は、通常よりも多くの帯域幅が必要になります。
デイジーチェーンで複数モニターを接続する際は、この点も考慮に入れる必要があります。
DSC(Display Stream Compression)について
DSCは、VESA Display Stream Compression標準に基づく「視覚的にロスレス」な圧縮技術です。
DSCのメリット
・帯域幅を約3分の1に圧縮可能(圧縮率は調整可能)
・視覚的にはほぼ劣化なし(一般的な使用では判別困難)
・4K 144Hz、8K 60Hzなどの高帯域幅が必要な映像に対応可能
・DP 1.4以降で標準サポート
DSCの注意点
・GPU、ケーブル、モニターの全てがDSCに対応している必要がある
・一部のプロフェッショナル用途(医療画像、色校正など)では使用を避けるべき場合がある
・ゲーミング用途では一般的に問題なし
最新バージョン「DP 2.1」で知っておきたいこと
ここでは、DP 2.1導入時点/近未来で知っておきたいポイントを整理します。
- 最大帯域が「約80 Gbps」まで到達:4レーン×20 Gbps(UHBR20)で理論80 Gbps。
- 圧縮技術DSC(Display Stream Compression)サポートが前提化:高解像度&高リフレッシュレートで映像信号を可搬にするため、DSCを使う製品が今後主流。
- USB-C/USB4との親和性が強化:DP 2.1ではUSB-C(Alt Mode)やUSB4トンネリングとの整合性を高め、1ポートで「映像+データ+給電」がより実用的に。
- 新しいケーブルカテゴリー「DP 40/DP 80」等:UHBR10(40 Gbps)用「DP40」、UHBR20(80 Gbps)用「DP80」などが規定されています。
- 普及にはタイムラグあり:実際にDP 2.1に完全対応したモニター・GPU・ケーブルが揃うまでには時間がかかっています。
これらを踏まえると、現状「4K/240Hz」「8K/60Hz」「3画面以上構成」など先端用途を狙う方にはDP 2.1対応も視野に入れたほうが良いですが、一般的な4K/60Hz+2画面用途ならDP 1.4でも十分な性能を発揮できます。
確認問題:Windows 開発キット 2023の出力仕様
筆者のメイン機「Windows 開発キット 2023」は、以下のような出力仕様になっています。

【問題】
Windows 開発キット 2023に4K 60Hzモニターを2枚接続したい。
条件を満たし、どちらも4K 60Hzで表示できる接続方法をすべて選びなさい。
【条件】
・出力元スペックは上記画像に準ずる
・ケーブル・ハブはすべてDP1.4以上対応
・GPU/SoCは「4K×2+FHD×1」の同時出力が可能
【選択肢】
① USB-Cポート2つを使い、USB-C→DisplayPortケーブルでそれぞれ4Kモニターに接続
② USB-C→DisplayPortケーブルで1台、もう1台をデイジーチェーンで4Kモニター同士をDisplayPortケーブル接続
③ USB-C→DisplayPortハブ(MST対応)を使用し、2台の4Kモニターをそれぞれ接続
④ miniDPポートで1台4Kモニター、USB-C→DisplayPortでもう1台4Kモニターに接続
⑤ miniDPポートで1台4Kモニター、もう1台をそのモニターからデイジーチェーン接続(4K同士)する
【各選択肢の解説】
① USB-C ×2でSST接続
仕様を見ると、USB-Cポート×2でも、映像ストリームは1系統しか割り当てられておらず、SST接続で4K60Hzを2枚同時出力することはできません。
→ ×
② USB-C→4K + デイジーチェーンで4K
こちらはMSTを利用したデイジーチェーン構成。
帯域的・仕様的に4K60Hz×2枚は可能と判断できます。
→ ○
③ USB-C→DisplayPortハブ(MST対応)で2台4K
DisplayPortハブがMSTに対応しており、USB-Cポートから4K×2出力可能。
→ ○
④ miniDP → 4K + USB-C → 4K
miniDP(通常DP1.2相当)をSSTで4K60Hz出力 ×1、USB-CをSSTで4K60Hz出力 ×1、合計2台4K出力可能。
→ ○
⑤ miniDP → 4K + デイジーチェーンで4K
miniDP端子がMST(デイジーチェーン)構成でも4K×2を帯域的に満たす仕様ではないため、4K×2同時出力は不可能と判断。
→ ×
【正解】②・③・④
Windows 開発キット 2023は「4K×2枚出力可能」とされていますが、実際にはSST・MST・映像ストリーム数・ケーブル仕様・ポート仕様を正しく理解しておく必要があります。
筆者も当初、USB-Cに4Kモニター+FHDモニターをそのまま差し込んでしまい、4K側がなぜかFHDに落ちてしまい途方に暮れました。
結論としては、
・USB-Cで複数モニターを活用するなら「デイジーチェーンまたはMSTハブ」が事実上必須
ということですね。
また、今後4K240Hzや8K60Hz以上、3画面構成を狙うなら、DP 2.1対応機器・ケーブルを検討する価値があります。
実用的な推奨構成例
用途別に、実際に動作する推奨構成をご紹介します。
構成例1:オフィスワーク向け(FHD × 3画面)
・PC環境:Windows PC、DisplayPort 1.2以上のGPU
・モニター:FHD(1920×1080)60Hz × 3台、MST対応
・接続方法:デイジーチェーン(PC → M1 → M2 → M3)
・必要帯域:3.20 Gbps × 3 = 9.60 Gbps(DP 1.2の17.28 Gbpsで十分)
・ケーブル:DP 1.2認証済み、各2m以内
ポイント:FHD 60Hzは帯域幅が少ないため、DP 1.2でも余裕を持って3画面接続可能。コストパフォーマンスに優れた構成。
構成例2:クリエイター向け(4K × 2画面)
・PC環境:ハイエンドPC、DisplayPort 1.4のGPU
・モニター:4K(3840×2160)60Hz × 2台、MST対応
・接続方法:デイジーチェーン(PC → M1 → M2)
・必要帯域:12.54 Gbps × 2 = 25.08 Gbps(DP 1.4の25.92 Gbpsでギリギリ)
・ケーブル:DP 1.4認証済み、高品質、各1.5m以内推奨
ポイント:DP 1.4の帯域をほぼフルに使用。色精度が重要な場合はSST(個別接続)も検討。HDR使用時は帯域不足の可能性あり。
構成例3:ゲーミング向け(4K + FHD)
・PC環境:ゲーミングPC、DisplayPort 1.4、G-Sync/FreeSync対応GPU
・モニター:4K 144Hz(メイン)+ FHD 60Hz(サブ)
・接続方法:SST個別接続(デイジーチェーンは使用しない)
・理由:G-Sync/FreeSyncを使用するため、メインモニターはSSTで接続必須
ポイント:ゲーミング用途ではMSTのデイジーチェーンは避け、各モニターを個別に接続。メインモニターで可変リフレッシュレートを活用。
構成例4:ノートPC + 外部モニター(4K × 2画面)
・PC環境:USB-C Alt Mode対応ノートPC(DP 1.4相当)
・接続方法1:USB-C → MSTハブ → 2台の4Kモニター
・接続方法2:USB-C → 4Kモニター1 → デイジーチェーン → 4Kモニター2
・必要帯域:12.54 Gbps × 2 = 25.08 Gbps
ポイント:ノートPCの場合、USB-CポートのDP対応バージョンを事前に確認。Thunderbolt 3/4対応なら余裕あり。
構成例5:ハイエンド(4K 144Hz × 2画面、DSC使用)
・PC環境:最新ハイエンドPC、DisplayPort 1.4 + DSC対応GPU
・モニター:4K 144Hz × 2台、DSC対応
・接続方法:個別接続(SST) + DSC有効
・必要帯域:約30 Gbps × 2(DSC非使用時) → 約10 Gbps × 2(DSC使用時)
ポイント:DSCを使用することで、DP 1.4でも4K 144Hzの2画面出力が可能。GPU、ケーブル、モニターの全てがDSC対応必須。
主要GPU/SoCのDisplayPort対応状況
主要なGPU・SoCのDisplayPort対応状況をまとめました(2024年時点の情報)。
NVIDIA GeForce(デスクトップGPU)
| GPU世代 | DP バージョン | 最大同時出力 |
| RTX 40シリーズ(Ada Lovelace) | DP 1.4a(DSC対応) | 4画面 |
| RTX 30シリーズ(Ampere) | DP 1.4a(DSC対応) | 4画面 |
| RTX 20シリーズ(Turing) | DP 1.4(DSC対応) | 4画面 |
| GTX 16シリーズ | DP 1.4 | 3〜4画面 |
AMD Radeon(デスクトップGPU)
| GPU世代 | DP バージョン | 最大同時出力 |
| RX 7000シリーズ(RDNA 3) | DP 2.1(UHBR13.5) | 4画面 |
| RX 6000シリーズ(RDNA 2) | DP 1.4(DSC対応) | 4画面 |
| RX 5000シリーズ(RDNA) | DP 1.4(DSC対応) | 4画面 |
注目:AMD RX 7000シリーズは、消費者向けGPUとして初めてDisplayPort 2.1に対応しています。
Intel Arc(デスクトップGPU)
| GPU世代 | DP バージョン | 最大同時出力 |
| Arc A770 / A750(Alchemist) | DP 2.0(UHBR10) | 4画面 |
| Arc A380(Alchemist) | DP 2.0(UHBR10) | 4画面 |
統合GPU・SoC
| プロセッサ | DP バージョン | 最大同時出力 |
| Intel Core 14世代(Meteor Lake) | DP 2.1 | 4画面 |
| Intel Core 13/12世代 | DP 1.4 | 3〜4画面 |
| AMD Ryzen 7000シリーズ(統合GPU) | DP 2.0 | 4画面 |
| Apple M3 / M2 / M1シリーズ | USB-C経由でDP 1.4相当 | M1: 2画面、M2/M3: 2〜3画面(モデル依存) |
| Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus | DP 1.4(USB-C経由) | 3画面 |
注意点:
・上記は理論的な最大値であり、実際の対応状況はマザーボードやノートPCの実装に依存します
・macOS(Apple Silicon)はMST方式のデイジーチェーンに非対応のため、複数モニター接続には個別ポートまたはThunderbolt Display使用が必要
・最大同時出力数は、解像度や帯域幅によって制限される場合があります
まとめ
DisplayPort周辺の規格は複雑ですが、ポイントを押さえておけば、適切な構成を組むことができます。
DisplayPort周辺の規格は複雑ですが、理解すれば私のような配線/接続ミスを避けられます(笑) ぜひ参考にして頂ければ幸いです。